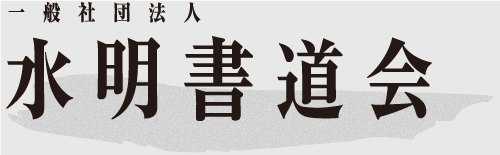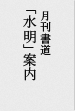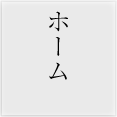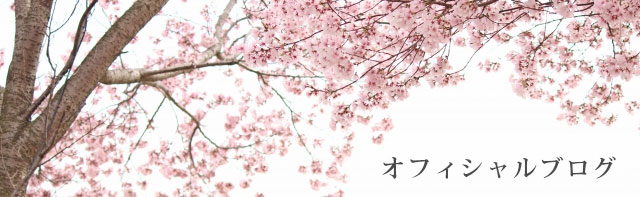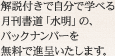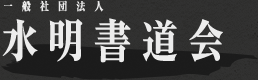うたごよみによせて その5「亀」
青もみじの美しい季節となりました。
インスタ映えで話題の京都八瀬の瑠璃光院の青もみじ。今は浄土真宗のお寺ですが、もともとは実業家の別荘として造営され、1万2000坪に数寄屋造りの建物と日本庭園があります。書院からの眺めの美しさを見ると人気も納得します。


さて、今月のテーマは、「亀」。
「鶴は千年、亀は万年」といわれるように、長寿で縁起の良い生き物とされています。これは、中国から伝わったもので、漢の時代(紀元前130年ごろ)の書物に書かれたことからとされています。
また、神話にたびたび登場します。中国には不老不死の仙人が住む蓬莱山という山があり、その仙人の使いが亀であったことから、長寿、不老不死のイメージが定着したと言われています。
中国神話に登場する巨大な亀、霊亀(れいき)は、甲羅に蓬莱山を乗せた姿で絵などに描かれます。
万葉集には、亀を詠んだ歌は長歌の二首しかありません。そのひとつは、恋の病に苦しむ人を占うために亀の甲羅を焼くというものです。
古今和歌集でも多くはありません。こちらは長寿を祝う歌となっています。
「亀の尾の山の岩根をとめて落つる 滝の白玉千世の数かも」
(大意:亀尾山の岩間を伝わって流れ落ちる滝の白玉は何と美しいのでしょう。その無数の白玉がすなわちあなた様の長いお年の数なのです。)
在原滋春作で、詞書きに「藤原三善が六十賀によみける」とある通り、長寿を祝う歌で、「鶴亀も千年の後は知らなくに 飽かぬ心にまかせ果ててむ」
(大意:鶴や亀のように千年長生きしてしても、誰も知らないのだから、生きることに飽きない心に任せて、生きたいだけ生きて果てましょう)
などがあります。
俳句の世界では、「亀鳴く」が春の季語として親しまれて、「亀鳴く」の俳句を検索すると、たくさん出てきます。
鎌倉時代の歌人藤原定家の三男の為家が和歌ではじめて用いたと言われています。
その歌は「川越のをちの田中の夕闇に何ぞと聞けば亀のなくなり」です。
亀は実際には鳴きませんが、春ののどかな昼や朧の夜に亀の鳴く声が聞こえるような気がするとされ、この遊び心や想像力が俳諧の世界で好まれ、動物を対象にした春の季語のひとつとして定着したと言われています。
句例として、あげてみます。
亀鳴くや皆愚なる村のもの (高浜虚子「五百句」)
亀鳴くと嘘をつきなる俳人よ (村上鬼城「鬼城句集」)
亀鳴くや月暈(げつうん)を着て沼の上 (村上鬼城「鬼城句集」)
「松竹梅」「鶴亀」と、縁起物が続いています冷泉貴実子氏の「うたごよみ」。
来月は何だろうと今から楽しみです。
2025年5月 編集部 北川詩雪